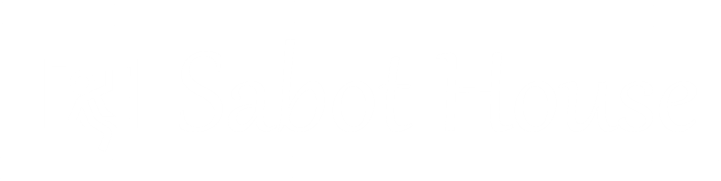【ネタばれ無】
多重人格という症例は、フィクションの世界で多く扱われる題材の1つであるといえるだろう。
古くはスティーブンソンの小説『ジキル博士とハイド氏』、ジム・キャリーのコメディ映画『ふたりの男とひとりの女』、高橋和希による漫画『遊☆戯☆王』等、様々な媒体であらゆるタイプの多重人格者が描かれてきた。
『スプリット』(原題:Split)も、多重人格を題材にした映画のひとつだ。本作は2016年公開のアメリカ映画で、M・ナイト・シャマラン監督がメガホンを取り、監禁された3人の女子高生とジェームズ・マカヴォイが演じる、23の人格を持つ誘拐犯を描いたサイコスリラー作品だ。
役者の演技力が試されることや、あまり身近にはなくセンセーショナルな疾患であるため、多重人格は “コンテンツ” として人気である、という見方ができる。
人々は多少なりとも「変身願望」を抱いている。他の誰かになりたいからこそ、憧れの人の服装や言葉を真似したり、コスプレが流行ったりするのだ。
今回は「変身願望」に着目して、多重人格というコンテンツがなぜ人気なのかを考えてみよう。
解離性同一性障害とは

まずは、多重人格を考える上で解離性同一性障害について、簡単に説明をしよう。
解離性同一性障害(Dissociative Identity Disorder ; DID)とは、極度のストレスを回避するため、無意識の防衛反応により、その時の感情や記憶を切り離してしまう精神疾患だ。その感情や記憶が人格を持つことで、人格が分裂(Split)することにより発症するといわれている。
国際疾病分類であるICD-10では、解離性障害のひとつのカテゴリーとして分類されている。心的ストレスをきっかけにその出来事の記憶を無くす「解離性健忘」や、自分自身の心が体から離れ、あたかも自分を外から眺めているように感じられる「離人症」も解離性障害の一種である。
俗に「多重人格」として知られるものは、この疾患のことを指している。
ストレスから身を守るための防衛反応だが、ここまで極端ではなくとも、私たちは潜在的に「防衛機制」というものが備わっている。
防衛機制とは

「夢判断」で有名な精神分析学の創始者である、ジークムント・フロイトのヒステリー研究から始まり、彼の娘であるアンナ・フロイトが整理をした概念である。
幼児の精神分析から整理された理論だが、幼児だけでなくどの世代でも自分自身を守るために様々な「防衛機制」でストレスから自分を守っている。これは、人間に備わった本能だと言える。
防衛機制の種類と例について、下記の表を確認していただきたい。
※分類については諸説あり。
| 種類 | 特徴 | 例 |
| 合理化 | 自分なりに理由をつけて、都合のいいように正当化する。 | テストの点数が悪かったのは寝不足のせいだと言い訳する。 |
| 抑圧 | 認めたくない欲求や衝動を意識にのぼらないようにする。 | 不都合な過去を忘れ去る。 |
| 否認 | 現実を受け入れずに拒否する。 | 病気の告知を受けても、自分にそんなことが起こる訳がないと認めない。 |
| 退行 | 甘える、駄々をこねる等、幼児に戻ったような行動をする。 | 幼児プレイにはまる中年。 |
| 反動形成 | 知られたくない欲求と正反対の行動をすることで、本当の自分を隠す。 | ツンデレ。 |
| 投影 | 自分の認めたくないことを、他者の中に原因があるとして非難する。 | 自分が嫌っている相手について、相手が自分を嫌っていると思い込む。 |
| 置き換え | 受け入れがたい負の感情を他の対象に向ける。 | ジャイアンにいじめられたストレスで、のび太をいじめるスネ夫。 |
| 補償 | 欠点を他の得意なことでカバーする。 | 勉強はだめでも、スポーツはできる、と納得する。 |
| 逃避 | 不安等から逃げ、心の安定を図る。 | 空想の世界に逃げ込む。 |
| 代償 | 本来の欲求よりも獲得しやすい代わりのもので我慢する | 第一志望を早めに諦めて第二志望の学校に進学する。 |
| 昇華 | 欲求を社会的に承認される形で行動に変える。 | 性的欲求を絵画などの芸術で表現をする。 |
| 同一視 | 他者の特徴を取り込んで、その対象と同一化すること。 | 憧れの俳優と同じ服やアクセサリーを身に着ける。 |
防衛機制について知らなかった人でも、上記の表の中に誰もが心当たりがある項目が見つかるだろう。
今回は表の一番下に記している「同一視」に着目していきたいと思う。
コスプレの心理

他の誰かになりたい、憧れの誰かみたいになりたい、という変身願望をお持ちの方も少なくはないだろう。
ここからは私の持論になるが、コスプレイヤーがコスプレする心理としては、防衛機制の「同一視」が強く働いているのではないかと考えられる。ストレスや欲求をコスプレという形で表現をするのは、良い「昇華」の形でもある。
アニメや映画の登場人物等の個性を自分の中に取り入れて、自分を高めようとする。自分にはないものを獲得したいという願望を、コスプレという形で表現しているのだ。
コスプレをしたことがない人でも、もっと綺麗に、可愛く、かっこよくなりたいという願望は持っているだろう。自分が持っていない容姿や能力を持っている人に憧れを抱いたことが一度もがないという人とは、少なくとも私は出会ったことがない。
本能である防衛機制と変身願望が密接に関わっている。そのため、人は誰しも多少なりとも。変身願望を持っているものだと私は考えている。
多重人格というコンテンツ

随分と遠回りになってしまったが、人は潜在的に変身願望を持っているという仮説を元に、多重人格というコンテンツの人気を考えてみよう。
多重人格のキャラクターは、正義であれ悪党であれ、別人格が本来の人格よりも過激な活躍をする姿が描かれている。そして、その多くでは別人格の出現による逆転劇を描くことが多い。
もしも、自分が失敗したり、勝てない相手に遭遇したりした時、一発逆転ができれば……と考えることがあるだろう。もし、状況を覆せる存在が自分の内に隠れていれば好都合だ。
現状に対する不満に対して、さながら変身を遂げて状況を逆転させる。そんな展開が多いのが “多重人格もの” であり、観客にとっては共感と憧れの的になりやすいのではないだろうか。
上手くいっていない方の人格に自己投影をし、別人格の方への同一化を望む。そうしたプロセスこそ、変身願望を持つ我々がコンテンツとしての多重人格に魅力を感じる要因だろう。
最後に
コンテンツとしての「多重人格」を楽しむこと自体は良いが、実際に解離性人格障害を患い、苦しんでいる患者がいることも忘れてはいけない。
多重人格のキャラクターに憧れていたとしても、その疾患を持つ人が抱える苦しみまでは理解できるとは限らない。
映画等のコンテンツで、病気や障害を知るということはとても良い機会である。しかし、フィクションでの知識と現実にはやはり違いがある。
なので、 “知る” という経験の後にはその知識を深めることが大切だ。
DIDについての知識を深めるのに役立つサイト、書籍を紹介しよう。
あなたが知識を持つことで、もしも将来DIDの患者やその傾向がある人と出会った時に、その人の助けになることができるかもしれない。