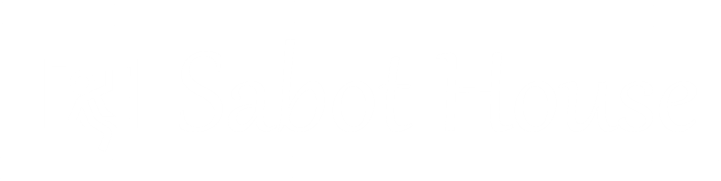【ネタばれ有】
『最強のふたり』(原題:Intouchables)は2011年のフランス映画。頸椎損傷で体に障害を持つ富豪のフィリップと、貧困層出身で前科のある黒人青年ドリスの交流を描いたものだ。
実話を基にした物語であり、障害者と介護者、白人と黒人、富豪と貧民、性格も環境も対極にあるふたりの交流の中に差別、偏見について考え直すヒントが多く提示されている。
今回はこの作品を紹介しながら、「善意の偏見」とは何か考えていこう。

ふたりの出会い ~フィリップの孤独と対等な関係~

物語は、富豪のフィリップが新しい介護者を募集するところから始まる。介護資格を持つ経験者達が職を求めて面接を受けに来るが、彼らはフィリップの隣にいる面接官としか対話をしていない。
採用されれば雇い主になるフィリップの顔をほとんど見ていないのだ。面接者たちはフィリップを、社会的に弱い立場にある「障害者」として認識していたように感じられる。フィリップを対等な立場にいる一人の人間として捉えることができなかったために、彼らはフィリップとまともに顔を合わせられなかったのだ。
そんな面接に、失業手当だけが目当てのドリスが現れる。彼は実に素直に、「就職活動の証明書が欲しいだけだ」と言い放つ。しかしドリスは他の求職者とは違い、フィリップの目を真っ直ぐに見て、気軽に話をしたのだ。受かる気のない面接だからこその振舞いではあったのかもしれないが、そこには対等な人間同士の対話があった。
ドリスには「障害者」という概念がそもそも無かったのだろう。彼はは誰が相手でも友人の様に気兼ねなく話をする。そのような振舞いが失礼にあたる場合もあるかもしれない。しかしフィリップは、単なる介護者としてではなく、一人の人間としてドリスに興味を持つことになる。
フィリップがドリスに惹かれた背景には、フィリップが抱える大きな孤独がある。富豪であり寡夫であり、その上障害者であるフィリップには、対等に接してくれる人がいないのだ。フィリップは、この孤独から解放されるための糸口をドリスに見出したのかもしれない。彼はついに、ドリスを介護者として雇うこととなる。
容赦のないドリス
介護経験もなければ、業務内容にすら興味もないドリス。麻痺のあるフィリップの足にわざと熱湯をかけたり、チョコレートは健常者用だからあげない、というどぎついジョークを言い放ったり、ドリスの振舞いには本当に容赦がない。
しかし、障害者のことを全く知らないドリスだからこそ、車椅子対応の福祉車両であるリフト付きの車を見たドリスの反応もまた容赦がなかった。
「馬みたいに荷台へ載せろと?」
車椅子のまま乗車できる福祉車両は、確かに実用的で利便性が高い。だが、バックドアから乗車することは果たして人間的だろうか。「障害者だから仕方がない」と心のどこかで思っていると、そんな当たり前なことにすら気が付くことが出来ない。ドリスは、障害者に対して無知であるからこそ――何の先入観も持っていないからこそ――そんな疑問を素直に口にすることができたのだろう。
そうして、ドリスはフィリップを福祉車両にではなく、マセラティの助手席に乗せる。助手席でのフィリップはドリスに初め字が差別のもとになってるわけじゃないから字が差別のもとになってるわけじゃないからて笑顔を見せる。頸椎損傷の原因となった事故の前は、車が好きだったのだろう。しかし、障害を負ってからというものの、駐車場に並ぶ福祉車両以外には乗れなくなってしまった。そんな思い込みを崩すことが出来たのも、ドリスの容赦の無さのおかげであろう。
二人の価値観の違い

絆を深めていくふたりであるが、趣味嗜好は正反対だ。
白地に赤のしみの抽象画を見てフィリップは感動するが、ドリスは鼻血の跡だと笑う。
フィリップがドリスにクラシックを聞かせてみても、ドリスには「熊蜂の飛行」が「トムとジェリー」のようだと言う。
フィリップが好きなパラグライダーも、ドリスにとっては恐ろしいものでしかない。
価値観の違いを、時に批判的な言葉すら使いながも、ふたりは楽しそうに語り合う。彼らは、「人間はそれぞれ違うもの」ということを分かっているのだ。
寛容であることは、心地の良い円滑な人間関係を築く秘訣ではないだろうか。
善意ゆえの偏見
フィリップがドリスについて友人に語った時、シンプルだが印象深い言葉を使った。
「彼は私に同情していない」
ドリスは、フィリップのことを憐れんでいない。フィリップは、自分を障害者としてではなく、対等な人間として接するドリスとの関係を大切にしている。だからこそ、ふたりの関係には余計な「気遣い」がない。
確かに、気遣いは人間関係の中で大切なものである。しかし行き過ぎた気遣いは、いつの間にか「善意ゆえの偏見」になってしまう。
例えば、鬱病を持つ人に「がんばれ」という言葉をかけるのは御法度とされている。必要以上のプレッシャーを与えないためであり、それは必要な気遣いである。
しかし、その気遣いが行き過ぎると、鬱病の人には話しかけないでおこうという考えが生まれてしまうことがある。鬱病を持つ人との接し方がわからないという声をよく耳にする。何と声を掛けたらいいのか、または話しかけない方がいいのか。話しかけるなら、どんな話題が良いだろうか、鬱病を連想させるような発言には気にしないといけないのか。こうして悩むことは、傷つけないための気遣いだろう。
しかし、鬱病を持っていても同じ人間だということを忘れてはないだろうか。
他人に対する接し方は人それぞれである。気遣いをしすぎる事で特定の人を排斥してしまうことは善意から生まれる偏見なのではないだろうか。善意による過剰な気遣いが、偏見を生み出しているように感じてならない。
障害者への先入観

私たちは、障害者や障害者をサポートする人々を、「苦労人であり善人」という型に当てはめて考えがちだ。彼らの苦労や美談を賛美するチャリティ番組などが、その最たる例だろう。
さて、フィリップとドリスはどうだろうか。確かに彼らは苦労をしている。しかし、障害者であるからと言って、私たちが想像するような「障害者」像に当てはまるような「善人」ではない。映画の冒頭ではスピード違反を犯した後に、障害者であることを逆手に取って警察を弄んでいる。更に、大麻をふたりで吸うシーンまである。
このような悪行も、彼らの一面に過ぎない。
誰かに優しくすることもあれば、意地悪をすることもある。彼らは私たちと何ら変わらない、様々な顔を持つ人間なのだ。多面的な人間の一部だけを見て過度な期待をしてしまうことは危険だ。そんな多面的な人間の一部だけを見て、その人の人となりを判断するのは危険だ。
これは、私達の普段の人間関係にも共通している。
例えば、家族や友人、恋人との関係で、自分の思い通りの言葉や反応が返ってこなくて落胆する経験は誰にでもあるだろう。先入観や過度な期待が先行してしまい、「こうであってほしい」という理想を押し付けてしまう。
先入観や偏見は誰しもそれぞれの形で持っている。それは悪いことではない。先入観や偏見を持っている自分自身を自覚することが、『最強のふたり』のような関係を築くための第一歩ではないだろうか。
堅苦しい話を重ねたが、この映画は気持ちが明るくなる楽しい映画である。少し寂しい日には是非この映画に元気を貰ってみては如何だろうか。