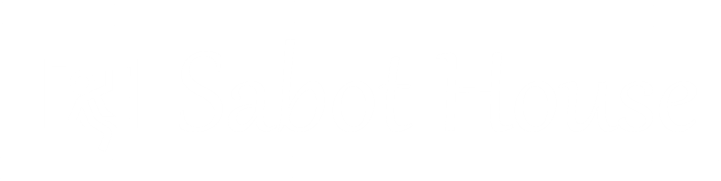【微ネタばれ有・グロテスクな画像有】
アメリカの人は幽霊になっても陽気――。
自己主張の激しい心霊写真や、訪れる人を楽しませようとしているとしか思えない心霊スポット。一昔前に流行った心霊番組で、アメリカにおける霊がそのように取り上げられていたのを目にした。
ダイバーシティの重要性が唱えられているこの時代に、「アメリカ人は~」といった括り方をして偏見を煽っても良いのか……と疑問には思ったが、どうやら幽霊だけは未だに世間の寛容さを享受できていないようである。
私は、アメリカンな霊に対する偏見を払拭する手立てを考えた。そこで閃いたのが、「ジャパニーズホラー映画とハリウッドリメイク版を比較する」という手法である。
同じ、ないし似た物語を映し出す2作品を比較することで、「日本もアメリカも、幽霊は幽霊だ」という結論を導けないかと考えたのである。
タイトルの時点で既にこの試みが失敗であったことは明白だが、比較を通してホラー映画の演出を語る上で欠かせない要素を見出すことができた。騙されたと思って、しばしお付き合いいただきたい。

比較対象とあらすじ
今回私が比較対象として選んだものは、『着信アリ』(以下、日本版)と、そのハリウッドリメイク版である『ワン・ミス・コール』(原題:One Missed Call。以下、米国版)の2作品だ。
日本版、米国版の概要はこうだ。
ある日突然、自分の携帯が不気味な着信音を鳴らして震え出す。電話を取ろうとすると着信音は止み、一通の留守電が残されている。電話は自分の番号かけられたものであり、内容は自らの悲鳴のみ。その電話を受けたものは、メッセージが発信された時間になると死ぬ。さらに、その呪いは犠牲者の携帯から次の連絡先を選び出し、次なる呪いの電話をかける……。
2作品は、犠牲者となる人間の関係などに若干の相違は見られるものの、あらすじに大きな違いはない。
物語に大幅な違いが無いからこそ、日本の霊と欧米の霊がどのように異なるのかが検証できる、という算段だ。
結論から言うと、日本の霊とアメリカの霊は犠牲者へのアプローチが極端に異なる。
偏見をなくす! と意気込んで2作品を鑑賞した筆者だったが、「あらすじ以外全部違うじゃねーか」と投げやりになってしまったレベルだった。

比較記事なんて執筆した日には、かえって偏見を深めることになりそうだ。
いやしかし、どこがどう違うのかを明らかにして、違いを受け入れ合うことこそダイバーシティではなかろうか。そう、みんな違ってみんな良いのだ。
ということで気を取り直し、最も目についた違いから解説していきたい。
序盤からビジュアルで攻めてくる米国
まず第一に、米国版はビジュアルを使った恐怖演出が非常に多い。
日本版では呪いの電話がかかってきた後、受信者がただひたすら怖がっているだけだった。『シャイニング』などから脈々と受け継がれている「怖がっている姿が怖い」という演出だ。
ところが米国版では、大量のムカデや不気味な少年、目の代わりに口がある女性など、犠牲者を直接怖がらせる幻覚が幾度も起こるのだ。

また、犠牲者が死ぬ瞬間の演出も米国版の方が随分派手だ。
劇中で描かれる二番目の犠牲者を例に挙げよう。日本版では異空間に続くエレベーターに飲み込まれるという摩訶不思議な死に方をしていた。
ところが米国版になると、“工事現場での爆発により吹き飛んだ鉄骨が刺さって死ぬ” というド派手な殺られ方に様変わり。
米国版では他にも、女性が電車に轢かれる様子を映し続けていたり、怪物が近寄るスピードが速かったり、窓ガラスを大量に割ったりと、とにかく “ビジュアルで分かりやすい” 恐怖表現が目立つ。
不気味な死に方よりも派手な死に方がより怖い、と言わんばかりだ。
スタイリッシュに攻めてくる欧米

邦画と洋画では全体的に異なる点だが、2作品はカメラワークも全く違う。
米国版は、日本版に比べて圧倒的にカット数(画面転換数)が多い。あるシーンで比較してみよう。
主人公にも呪いの電話がかかってきた。主人公の協力者である男性が留守電を聞き直し、携帯を割って近くの水槽に突っ込む。
上記シーンは2作品どちらも50秒ほどのシーンだが、日本版では1カット。対して米国版では8カットも費やしている。
他のシーンで、米国版にのみ「怪物の目線(POV)」のカットがあるのも、特筆すべき違いだろう。
1カットが短かく、トントン拍子に話しが進むため、米国版は日本版よりも30分ほど上映時間が短くなっている。
これら撮影技巧の違いにより、米国版はテンポと臨場感が増した作品へと仕上がっている。
違いの根源は何なのか

似たような脚本から、なぜここまで異なる作品が生まれるのだろうか?
この疑問は、「映像文化の違い」と一言で片付けることもできる。事実、邦画は比較的カットごとの時間が長く、洋画は目まぐるしく場面が変わることが多い。CGの多用も、洋画の特徴だろう。
ただ、その回答だけだと面白くないので、ひとつ付け加えさせていただきたい。それは「製作費の違い」だ。
米国版の製作費は2,700万ドルほど(約30億円)とされている。日本版の製作費が公表されていないため、一概に比較することはできないが、邦画では巨額を投じたとされる『男たちの大和』の製作費が25億円程度と言われているので、米国版は比較的潤沢な資金のもとに製作されたことが伺える。
カット数を増やすためには同じシーンを何度も撮り直すか、カメラの台数を増やす必要があり、どちらも人件費がかかってしまう。幻覚をCGで表現するにしても、莫大な費用がかかる。
製作費という足枷がある日本版では、このような映像表現は非常に困難、というわけだ。
ホラー表現の革命は “低予算” だからこそ起こる

では、予算面で不利な状況に立たされている日本は、名作ホラー映画を作ることはできないのか?
否、ホラー映画史における “革命” は、むしろ低予算によって引き起こされていると明記しておきたい。
日本では、『カメラを止めるな』の大ヒットが記憶に新しいだろう。海外に目を向けても、『パラノーマル・アクティビティ』や『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』、『ソウ』など、低予算ながらホラー史にその名を刻んだ作品は多い。
『レディ・プレイヤー・ワン』内でのオマージュにより2018年に再び脚光を浴びた『シャイニング』も、予算が限られた中でホラー演出の模索を続け、「窓から差し込む光を紫色になるように現像する」という技巧を生み出したと言われている。
これは本来、撮影・フィルム現像のミスなのだが、キューブリック監督はこれを作品が持つ不気味さを表現する “演出” へと昇華した。

「必要は発明の母」とはよく言ったものだが、ホラー映画史に時折起こる革新は、まさにこの言葉を体現している。
事実、「演出の怖さ」に絞って日本版と米国版を比べてみると、CGやカット割りに制限のある日本版に軍配が上がる(個人差はあるかもしれないが)。
情報が限られているからこそ、画面で全てを説明しないからこそ、観客は「理解できないものを恐れる」ことができるのだ。
安易なシリーズ化やリメイクが多く、表現の焼き増しにあふれるホラー映画界隈だからこそ、一発逆転を狙うクリエイターは必要に迫られて革命を起こす。映画史全体を眺めてみても、これほど面白いジャンルはないだろう。
この記事を開いている今も、世界のどこかでは新しい表現方法が生まれている――そう考えると、ホラー映画を追い続けている私は鳥肌が止まらない。